| 加速する原子力発電所の開発 |
 7月に開かれる「北海道洞爺湖サミット」。ホスト国である日本の福田首相も4月に開かれたG8ビジネスサミット(主要国首脳会議)で「低炭素革命」と銘打ち、原子力をはじめとした新エネルギーの開発積極化を唄っていたが、北海道洞爺湖サミットでは改めて主要議題として取り上げられる予定であり、各国の原子力事業への取り組み強化につながるものと予想される。そうなれば元々、省エネルギー技術、排出ガス削減技術で世界最高水準を行く日本企業の出番増加が期待出来る。
7月に開かれる「北海道洞爺湖サミット」。ホスト国である日本の福田首相も4月に開かれたG8ビジネスサミット(主要国首脳会議)で「低炭素革命」と銘打ち、原子力をはじめとした新エネルギーの開発積極化を唄っていたが、北海道洞爺湖サミットでは改めて主要議題として取り上げられる予定であり、各国の原子力事業への取り組み強化につながるものと予想される。そうなれば元々、省エネルギー技術、排出ガス削減技術で世界最高水準を行く日本企業の出番増加が期待出来る。例えば日立製作所<6501>。米国のゼネラル・エレクトリック社(GE)と共同で、米国ミシガン州の原子力発電所を1基受注すると発表した。1520メガワット級の次世代の沸騰水型軽水炉「ESBWR」を受注する見込みで建設工事まで含めた総額は最大4000億円規模とみられる。9月に米原子力規制委員会(NRC)に建設・運転許可を申請し、稼働時期は2010年代半ばになる模様で今後の新規受注に弾みがつくものと見込まれる。
一方、東芝<6502>はカザフスタンの国営企業カザトムプラムと原子力分野の協力拡大に関する覚書を締結。カザトムプラムが採掘・加工する原発材料のレアメタル(希少金属)を安定的に調達する交渉を進める。東芝はカザトムプラムとすでに2007年4月、原子力分野で相互協力契約を締結しており、まず傘下の米原子力メーカー、ウェスチングハウス(WH)株を10%カザトムプラムに売却。さらに同社のウラン鉱山開発プロジェクトへの参加も決めている。今回の締結は、世界的な原発建設ラッシュによる争奪戦激化が見込まれる原材料調達にまで踏み込んだもので、東芝はWHと合わせて2015年までに39基もの大量の原子力プラントの受注を見込んでいることから、資源調達の面から原発事業を優位に進めていく方針である。
また三菱重工業<7011>は国内の加圧水型原子力発電プラントに強みを持ち、既に23基を稼動中。合計電気出力は約2000万KWに達するなど、国内の原発市場で高いシェアを誇るほか、米国市場にも本格参入を計画しており、2030年までに世界シェアを25%〜30%にまで引き上げる方針を発表、今後の事業拡大が見込まれる。
| 原料調達で商社も一役 |
原子力発電所の技術開発、建設そのものは主にメーカーの分野であるが、原料確保という面では実は商社が大きな貢献を果たしている。その中で住友商事<8053>はカザフスタンでウラン生産設備を本格稼動させた。今年度中に関西電力など原子力発電所を所有する顧客向けにウランの引き渡しを始める。2010年までには毎年1000トンのウランをフル生産する計画であり、鉱山寿命となる2022年までに総生産量は1万8000トンが可能と見積もる。また丸紅<8002>も東京電力<9501>や東芝<6502>とウラン鉱山開発事業を進めており、争奪戦が激化する中での資源調達企業、日本の原発開発のバックアップ企業として注目に値する。
| 原発設備を担う企業群 |
 原子力発電所の建設が世界規模で増加する中で、当然のことながら設備工事を請け負う企業の受注増加が見込まれる。東京エネシス<1945>は東京電力関連の原子力発電所の建設及びメンテナンス工事に強みを持つ。原子力施設の空調ダクト工事に強みを持つ新日本空調<1952>も受注増加が期待される。またポンプ・バルブ分野においては岡野バルブ製造<6492>が新潟県中越沖地震で全プラントが停止している柏崎原子力発電所において、期初に発生していなかった点検作業を伴う工事受注に成功、メンテナンス工事も好調に推移している。トウアバルブグループ本社<6466>は三菱重工業<7011>と協力し、原発向け高温高圧バルブに強みを発揮している。また宇野澤組鐵工所<6396>は原子力用真空ポンプ製造を強化し、今後の受注増加に備えているほか、帝国電機製作所<6333>は無漏洩ポンプ最大手で国内6割、世界4割と圧倒的なシェアを誇るのが強みであり、何れも要注目企業である。
原子力発電所の建設が世界規模で増加する中で、当然のことながら設備工事を請け負う企業の受注増加が見込まれる。東京エネシス<1945>は東京電力関連の原子力発電所の建設及びメンテナンス工事に強みを持つ。原子力施設の空調ダクト工事に強みを持つ新日本空調<1952>も受注増加が期待される。またポンプ・バルブ分野においては岡野バルブ製造<6492>が新潟県中越沖地震で全プラントが停止している柏崎原子力発電所において、期初に発生していなかった点検作業を伴う工事受注に成功、メンテナンス工事も好調に推移している。トウアバルブグループ本社<6466>は三菱重工業<7011>と協力し、原発向け高温高圧バルブに強みを発揮している。また宇野澤組鐵工所<6396>は原子力用真空ポンプ製造を強化し、今後の受注増加に備えているほか、帝国電機製作所<6333>は無漏洩ポンプ最大手で国内6割、世界4割と圧倒的なシェアを誇るのが強みであり、何れも要注目企業である。一方、原発増加に伴い、使用済み核燃料の廃棄及びリサイクルが大きな問題となってくる。そこで三井造船<7003>、日立造船<7004>、木村化工機<6378>は放射性廃棄物処理設備の開発や使用済み燃料リサイクル施設建設に注力しており、今後の受注増加が期待される。
このほかに原子力用模擬燃料集合体に強みを持つ助川電気工業<7711>、原子炉浄水系水処理プラントを手掛けるオルガノ<6368>、原子力発電所向けの高性能特殊ルツボを手掛ける日本ルツボ<5355>も注目していきたい。
| 貯蔵・輸送も重大なテーマ |
原子力発電所の増加に伴い、最も重大なテーマとして上げられるのが「安全性の確保」である。万が一にでも「放射能漏れ事故」が発生すれば近隣住民だけでなく、最悪の場合、地球規模での深刻な被害につながる可能性もあるだけに、その管理・貯蔵或いは輸送分野への投資は決して軽視出来ない分野である。
その使用済み燃料を貯蔵、輸送する際に使われる鋼鉄製の専用容器を「キャスク」と呼ぶが、そのキャスク分野に強みを発揮している企業が日立造船<7004>、木村化工機<6378>である。また東芝<6502>、三菱重工業<7011>は原子炉冷却設備及びその関連設備を格納する「原子炉格納容器」に強みを持つ。また使用済み核燃料の周囲に冷却材を循環させて崩壊熱を取り出す「原子炉圧力容器」は日本製鋼所<5631>が得意としており、何れも原発増加に比例してニ−ズの増加が確実視される。
また輸送面における企業として取り上げたいのが宇徳<9358>。原発大型設備の輸送・据付に実績があるほか、最近では格納容器備え付けの核燃料輸送にも注力しており、周辺銘柄として要注目である。
原油の高騰、世界規模での人口爆発、地球温暖化による環境異変への不安など、21世紀は如何に環境に負担をかけず、効率的なエネルギー生産を行えるかが、大きな鍵となっている。そういう意味で「原子力関連銘柄」は各国の政策的な後押しもあり、大きな事業の発展性を秘めている銘柄と言えよう。
提供 日本インタビュ新聞 Media-IR 2008.6 |特集

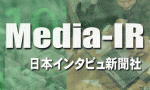

 現在、新興国を中心に、世界規模での産業の活発化と生活水準の向上に伴う電力需要が増加の一途を辿っている。生活水準の向上は地球の全人類が望むことであり、誰しもが豊かになる権利を持っているが、このことが同時に地球温暖化を加速し、深刻な気候変動に繋がる危険性を高めている。具体的な要因として、発電量増加に伴う石炭・重油の燃焼による二酸化炭素の排出増加、自家用車普及に伴うエンジンから排出される二酸化炭素・窒素酸化物等の増加、工業生産に伴って出される排ガスによる二酸化炭素の増加、ニュータウン開発・工場新設などに伴う二酸化炭素を消費する森林の減少などである。
現在、新興国を中心に、世界規模での産業の活発化と生活水準の向上に伴う電力需要が増加の一途を辿っている。生活水準の向上は地球の全人類が望むことであり、誰しもが豊かになる権利を持っているが、このことが同時に地球温暖化を加速し、深刻な気候変動に繋がる危険性を高めている。具体的な要因として、発電量増加に伴う石炭・重油の燃焼による二酸化炭素の排出増加、自家用車普及に伴うエンジンから排出される二酸化炭素・窒素酸化物等の増加、工業生産に伴って出される排ガスによる二酸化炭素の増加、ニュータウン開発・工場新設などに伴う二酸化炭素を消費する森林の減少などである。