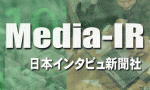提供 日本インタビュ新聞 Media-IR 2009.04 |特集
2009年04月
関西経済特集 Vol.3


| 恵まれた観光資源の活用が域内経済の活性化をもたらす | |||||||||
行政主導の景気対策に乗じて、或いはそれに対抗して民間ベースでも新たなサービスの展開が始まっており、例えば東日本旅客鉄道(JR東日本)<9020>は定額給付金対応として、JR東日本管内の指定席往復利用料金と1泊2日の宿泊代をセットにした割引旅行パックサービス「温泉がいい値」の発売を開始(利用可能期間は今年4月12日から7月17日まで)。また西日本旅客鉄道(JR西日本)<9021>は新幹線こだまの往復指定席料金が最大4割引となる「こだま指定席往復きっぷ」を発売(利用可能期間は今年6月30日まで)。さらにJR西日本・JR四国の全線及びJR九州の一部区間の新幹線・特急を含めた乗り放題切符「西日本パス」(利用可能期間は今年5月8日から6月29日まで)も合わせて発売するなど、今回の「政策特需」を逃すまいと、各社様々な工夫を凝らしている。 特に、今回の「政策特需」で需要増加の期待が高まっているのが「旅行・観光」分野である。前述した内需刺激策一つをとって見ても、「旅行・観光」需要の喚起が明白である。高速道路料金の上限1,000円は、従来なら控えていた遠方へのドライブを可能にするサービスであろうし、特に定額給付金については、もう二度と行われることはない一時金支給の可能性も高く、そうした意味でもせっかくの機会だからと、非日常空間を体験したいという人間心理に駆られる人も少なくないのではないか。 その「旅行・観光」という分野で最も多くの観光資源・観光客数を抱えているのが関西である。年間5,000万人(入込ベース)もの観光客が訪問する日本最大の観光都市・京都市をはじめ、古都奈良、商都大阪、港町神戸など、観光資源を多く抱える都市が在来線で1時間圏内のエリアにこれほど集積しているのは日本国内を見渡しても他に例がない。それどころか世界的に見ても希少なエリア特性を誇っていると言えよう。またもう少し広げて見渡せば、世界遺産の姫路城を抱える姫路市、同じく世界遺産である熊野古道(紀伊山地の霊場と参詣道)を抱える和歌山県など、観光対象エリアを挙げ出したら枚挙にいとまがない。何と言ってもこの国内の世界遺産の7割、また国宝・重要文化財の4割が関西2府4県に集積しているのである。 当然のことながら、関西エリアの経済再生・活性化を図っていく中で、この充実した観光資源を生かさない手はない。幸い、首都圏と並ぶ交通インフラ、宿泊施設を整えており、広域エリアから集客することは元来難しくはない。今後はソフト面を中心に、如何に関西が「旅行・観光」エリアとしてより魅力を高めていくことが出来るか否かで、今後の持続的な域内経済発展の成否に繋がると言っても過言ではない。 そこで今回は、景気対策の実行を追い風として、関西経済の発展に貢献する観光及び関連上場企業にスポットライトを当ててみたい。 【目次】 ・京都が持つ普遍的観光力 ・大規模イベント控える奈良 ・異国情緒あふれる港町神戸 ・外円部にも観光資源が広がる関西 ・関西観光の交通基点 大阪 |
|||||||||
| 京都が持つ普遍的観光力 |
 千年の都、京都。国内最多の17の世界遺産、建造物においてもこれまた国内最多の国宝・重要文化財を要するこの古の都は、年間5,000万人弱(入込ベース)に上る観光客を集める日本最大の観光都市でもある。当然のことながら、域内経済に占める観光産業への依存度は高い。そこで行政もさることながら、この街を舞台に活動する各企業も観光産業の発展に貢献するため、様々な企業努力を行っている。
千年の都、京都。国内最多の17の世界遺産、建造物においてもこれまた国内最多の国宝・重要文化財を要するこの古の都は、年間5,000万人弱(入込ベース)に上る観光客を集める日本最大の観光都市でもある。当然のことながら、域内経済に占める観光産業への依存度は高い。そこで行政もさることながら、この街を舞台に活動する各企業も観光産業の発展に貢献するため、様々な企業努力を行っている。まずは京都を訪問するにあたって、「お世話になる」のは交通機関である。西日本旅客鉄道(JR西日本)<9021>は前述したこだま往復割引切符や、乗り放題切符「西日本パス」(詳細は先の項を参照)の発売で遠方旅行者の取込みを図るほか、出発駅から京都駅までの普通車往復割引切符と食事券をセットした「京都散策 日帰りの旅」(発売期間:今年6月27日まで)、兵庫県の立花駅〜神戸駅出発限定で、設定区間の一日乗り放題切符「春の京都エコきっぷ」(発売期間:今年5月30日まで)を発売するなど、近距離旅行者の取り込みも同時に図っている。
一方、京都を訪問する観光客の6割強は、地元関西エリアからの訪問という現実を踏まえ、関西私鉄も京都観光の活性化が自社鉄道の乗客増に繋がると捉えている。京阪電気鉄道<9045>は京都市営地下鉄と京阪大津線の一日乗り放題切符や、グループ会社の京福電気鉄道<9049>が運営する嵐山電車、京都市営地下鉄及び京阪大津線の一日乗り放題切符をそれぞれ来年3月31日まで発売。さらには南海電気鉄道<9044>と共同で南海沿線エリアからの1日乗り放題割引チケット「京都みやこびと1dayチケット」を今年4月25日から7月5日まで発売を予定しており、大阪方面からの旅客需要喚起を図る。京阪電気鉄道及びグループ会社の運行するエリアには特に著名な観光スポットが多く、京都観光需要の増加が同社グループの収益に与える影響は大きい。
また阪急阪神ホールディングス<9042>傘下の阪急電鉄も著名観光名所である嵐山へ向かう阪急嵐山線に新型車両を導入、地元の通勤需要に応えるほか、サービス向上でさらなる同線を利用した観光客のさらなる増加を目指している。
観光地では土産物や食事も楽しみの一つ。贔屓の老舗等を知っているのであれば話は別だが、「特に思い当たるところがない」と言う観光客にとって百貨店は土産物を買う格好の場所。J.フロント リテイリング<3086>傘下の大丸や高島屋<8233>はそれぞれ京都店を中心街に構えており、食料品売り場の土産物コーナーやレストラン街での京都の老舗出店に力を注いでいる。また三越伊勢丹ホールディングス<3099>傘下の伊勢丹はJR京都駅構内に「ジェイアール京都伊勢丹」を出店しており、立地の特性を生かして特に土産物コーナーに力を入れている。同店のHP上でも「京味」というコンテンツを設けて売上増を図るなど、余念がない。
さらに全国規模で観光客を集客する京都にとって不可欠な存在はホテル・旅館である。老舗の京都ホテル<9723>は京都市内の中心部に2つのホテルを構え、観光客が多い特性を考慮して食事に力を入れるほか、京阪電気鉄道<9045>傘下の京都タワーが運営する「京都タワーホテルチェーン」は今回の定額給付金支給に照準を合わせた特別割引プランを充実させ、JR京都駅前に立地する好条件を強みに宿泊客増加を目指している。
一方、近畿日本鉄道<9041>はグループの近鉄ホテルシステムズが「ウェスティン都ホテル」という京都における最高級老舗ホテルを運営するほか、JR及び近鉄京都駅前にもホテルを構え、富裕層・ビジネス双方の需要に応える体制を確立している。さらに近鉄京都駅上に新ホテルの建設を決定し、京都におけるホテル業界のリーディングポジション確率を目指している。
そして西日本旅客鉄道(JR西日本)<9021>は、グループのジェイアール西日本ホテル開発がJR京都駅ビル内に「ホテルグランヴィア京都」を1997年より開業・運営しているが、今年春に全室リニューアルオープンした。リニューアルに伴い、全室宿泊料金を平均15から16%値上げに踏み切り、値下げの続く昨今では異例の方針をとったが、JR京都駅という抜群の好立地で、客室稼動はフル稼働状態が続いてきたこともあり、さらなる高級感とサービス向上を提供することで、今後は顧客単価の向上を目指す方針。
| 大規模イベント控える奈良 |
 一方、中心街はすっかりビルの波になってしまった京都よりも先に都(平城京)が置かれ、現在でも本当の意味で「古都」の風情を漂わせている奈良。この奈良も京都に勝るとも劣らない世界遺産、国宝・重要文化財を抱え、奈良市だけで年間1,300万人前後(入込ベース)の観光客が集まる日本有数の観光地である。ただ今まではなぜか、話題性・イベントが少なかったため観光客数が伸び悩み、また観光客の9割弱が「日帰り」という現実が、奈良の観光産業に停滞感を与えてきたのも事実である。
一方、中心街はすっかりビルの波になってしまった京都よりも先に都(平城京)が置かれ、現在でも本当の意味で「古都」の風情を漂わせている奈良。この奈良も京都に勝るとも劣らない世界遺産、国宝・重要文化財を抱え、奈良市だけで年間1,300万人前後(入込ベース)の観光客が集まる日本有数の観光地である。ただ今まではなぜか、話題性・イベントが少なかったため観光客数が伸び悩み、また観光客の9割弱が「日帰り」という現実が、奈良の観光産業に停滞感を与えてきたのも事実である。その奈良で来年1月1日から1年に亘って「平城遷都1300年祭」が開催される。地元奈良では勿論のこと、全国的に見ても2005年に開催された愛知万博以来の大型イベントとなる予定で、これを起爆剤として観光産業を営む企業も本腰を入れ始めた。
奈良の「足」とも言える存在の近畿日本鉄道<9041>。奈良県の主要スポットほぼ全てを網羅しており、実は観光スポットが分散している奈良をくまなく観光するには不可欠な「足」である。特に今年は3月20日に阪急阪神ホールディングス<9042>傘下の阪神電気鉄道が阪神なんば線を開通し、神戸・三宮駅から近鉄奈良駅までの相互直通運転を開始。今回の定額給付金支給と合わせて例年にない追い風が吹いており、来年のイベント開催にかけて県内区間への利用客数増加が期待出来る。
そのため、3日間乗り放題の「奈良世界遺産フリーきっぷ」をエリア別に3種類発売し、宿泊需要増加を狙う一方、日帰り観光客が多いことを逆手に取って、「奈良・斑鳩1Dayチケット」なる関西各私鉄・地下鉄から出発分を含めた1日乗り放題切符も発売。出発エリアによっては半額近い割引効果があり、関西エリア在住者に人気が高いことから、日帰り観光客数自体のさらなる増加も期待される。
一方の西日本旅客鉄道(JR西日本)<9021>。奈良方面への路線は少なく、網羅するエリアも少ないものの、新幹線と接続する新大阪駅や京都駅に繋がっている優位性を誇るほか、関西の玄関口とも言える大阪駅にも乗り換えなしで行ける強みを生かして、「奈良を歩こう」ブランドで、兵庫県内のJR駅出発を対象に割引切符を今年6月30日まで発売。阪神・近鉄連合の阪神なんば線に対抗するサービスを実施することで、近距離旅行者の獲得を目指す。
前述の如く、日帰り観光客が大半を占める奈良ではあるが、新線開通、定額給付金、高速道路料金値下げ、さらには来年始まる平城遷都イベントと、今年から来年にかけて遠方からの観光客を呼び込む材料が目白押しであり、宿泊業界も様々な工夫を凝らしている。
日本航空<9205>傘下のJALホテルズが運営する「ホテル日航奈良」は「阪神なんば線開通記念プラン」として兵庫県民を対象に宿泊料金割引を開始。また定額給付金特別プランも用意し、近距離・遠方双方の宿泊客呼び込みを図る。また西日本旅客鉄道(JR西日本)<9021>傘下のジェイアール西日本ホテル開発及び近畿日本鉄道<9041>傘下の近鉄ホテルシステムズが折半で出資する奈良の名門ホテル「奈良ホテル」も、「近鉄・阪神直通運転開始キャンペーン」としてスペシャルランチを用意し(但し今年4月30日迄)、客足の増加を図っている。
| 異国情緒あふれる港町神戸 |
 「港町」という言葉には何かしら人を惹きつける響きがあるものだが、その日本を代表する「港町」神戸も大変、観光スポットに恵まれた都市である。年間3,000万人弱(入込ベース)の観光客が毎年訪問しており、異国情緒溢れる町並みは古都である京都・奈良とは対極をなす魅力を放っている。背後にそびえる六甲山から見渡す街のロケーション、夜景の美しさは日本有数であろう。ファッション・スイーツなど、特に女性観光客からの人気が高いのは消費の面で強みと言える。
「港町」という言葉には何かしら人を惹きつける響きがあるものだが、その日本を代表する「港町」神戸も大変、観光スポットに恵まれた都市である。年間3,000万人弱(入込ベース)の観光客が毎年訪問しており、異国情緒溢れる町並みは古都である京都・奈良とは対極をなす魅力を放っている。背後にそびえる六甲山から見渡す街のロケーション、夜景の美しさは日本有数であろう。ファッション・スイーツなど、特に女性観光客からの人気が高いのは消費の面で強みと言える。アクセス面でも京都から鉄道で1時間以内、大阪からなら30分以内で訪問することが可能で、関西旅行のセットとして周遊可能な位置に所在している点も、有利に働いているうえ、今年3月20日には阪急阪神ホールディングス<9042>傘下の阪神電気鉄道が運営する阪神なんば線が、神戸市の玄関となっている中心部の三宮まで乗り入れを開始したことでアクセスが向上、例年以上に観光に力を注いでいる。
その阪神なんば線に相互乗り入れする近畿日本鉄道<9041>。同線開通に合わせて自社ホームページ上に相互直通運転による利便性の向上を積極的にアピールしているほか、新たに「阪神沿線おすすめ情報」というコンテンツを設け現地の魅力を伝えることで、神戸・阪神間への観光客誘致に一役買っている。特に今まで少なかった奈良方面からの観光客誘導という効果は大きいと考えられる。南海電気鉄道<9044>も地盤の難波に同線が乗り入れたことによる相乗効果を狙い、ホームページ上及びタウン誌「p+natts」にて神戸をカテゴリーに追加し、旅行需要の掘り起こしに協力している。
一方、西日本旅客鉄道(JR西日本)<9021>は今年4月1日から6月30日まで「兵庫デスティネーションキャンペーン」を実施。自社ホームページ上に独自コンテンツを貼り付け、大々的な観光客誘致を展開しており、それに伴い「神戸・姫路ぐるりんパス」などの新幹線を含む割引チケット販売増加に繋げることで、遠方旅行者の増加を目指す。また同社のグループ会社が運営する「三宮ターミナルホテル」は神戸の表玄関である三ノ宮駅に直結している利便性を売りモノに、キャンペーンと連動した割引宿泊プランや、定額給付金に因んだ「神戸牛ステーキ宿泊プラン」を設定し、JR西日本とのシナジー効果を狙う。
また阪急阪神ホールディングス<9042>傘下の阪急電鉄は「阪急阪神1dayパス」、「スルッとKANSAI神戸観光1dayクーポン」など、1日乗り放題の割引乗車券を充実させ、近距離旅行者の需要掘り起こしに努めており、同社の100%子会社の阪急阪神ホテルズが運営する「六甲山ホテル」が今年7月17日まで「定額給付金フェア」としてホテル内の各レストランのコース割引を開催、鉄道会社と連動した顧客増を目指す。
さらに全日本空輸<9202>のグループ会社が運営する「クラウンプラザ神戸」はJR新神戸駅に直結し、遠方旅行者需要の取り込みに最適な立地条件を整えているほか、阪神なんば線開通記念として、奈良県在住者限定で「食べ放題2食付」プランを実施。リピーター需要の高い近距離旅行者囲い込みの好機と捉え、サービス強化を図る。
土産物においても神戸は京都に負けない豊富さを誇る。J.フロント リテイリング<3086>傘下の大丸は主力店である神戸店が、観光客の集まる中華街「南京町」に隣接していることもあり、食料品売場において神戸土産の品揃えを充実させているほか、三井不動産<8801>が運営する「三井アウトレットモール マリンピア神戸」は今年3月28日から始まった高速道路料金値下げ効果で、明石海峡大橋の袂という立地条件も幸いし、休日には四国方面からの来店客数が大幅に増加。この3月には新商業棟も完成し、店舗数の増加も重なって大幅な収益増が期待される。
| 外円部にも観光資源が広がる関西 |
今まで取り上げた京都・奈良及び神戸は、何れも大阪を基点に片道1時間以内で収まるエリアであるが、もう少し視野を広げた周辺エリアを見渡しても、魅力的な観光資源・装置が豊富に存在する。
姫路は世界遺産の姫路城を抱え、その眼前に迫るように聳え立つ壮大なロケーションは多くの観光客を魅了し、地元の人々の誇りである。神戸の項でも取り上げているが、西日本旅客鉄道(JR西日本)<9021>が大々的に展開する「兵庫デスティネーションキャンペーン」の中で姫路の紹介を展開しており、観光客へのアピールを強化することで、神戸とセットにした割引チケットの販売増加に繋げている。
「紀伊山地の霊場と参詣道」の一つとして世界遺産に登録されている「聖地」高野山。ストレス社会の中、癒しを求めて精神世界を探求する観光客が近年増加している。南海電気鉄道<9044>はその高野山に向かう高野線において、観光列車「天空」を今年7月3日から定期運行することを発表した。山地に向かう列車として「木」を感じさせるデザインや展望デッキを設けることで、観光客の増加を目指す。
さらに日本一大きい湖、琵琶湖を抱える滋賀。「日本一」でありながら、全国的には地味な存在であったその琵琶湖が近年、都市近郊リゾートとして脚光を浴びるようになっている。京阪電気鉄道<9045>は湖を一望する高級ホテル「琵琶湖ホテル」を運営し、リゾート感覚を前面に打ち出したアピールを強化し宿泊客の増加を目指すほか、子会社の琵琶湖汽船が今年1月から新型クルーズ船「megumi(めぐみ)」の運行を開始。琵琶湖という天然資源を最大限に生かしたビジネス展開を強化することで観光客誘致に繋げている。
| 関西観光の交通基点 大阪 |
このように関西エリアには多くの観光都市・資源が存在しており、特に遠方旅行者の場合には、せっかくの機会ということで一円をセットで周遊したいというニーズも増加している。またそうした場合、如何に効率よくスポットを周るかが重要なポイントになる。そこで「交通基点」として注目されるのが大阪である。
地理的特徴として、大阪は先に取り上げた京都、奈良、神戸に取り囲まれるように位置しており、関西の大手私鉄全てが大阪の都心部に繋がるように路線網を形成しているほか、西日本旅客鉄道(JR西日本)<9021>もJR大阪駅を「関西の玄関口」と明確に位置付けるなど、紛れもなく関西・西日本の交通の中心都市である。そのため特に宿泊客の場合、大阪に軸足を置いて関西一円の各観光スポットを周遊することこそ、一番効率が良い方法と言える。新幹線もJR新大阪駅が西の基点になっている点も大きいうえ、大阪・関西両国際空港の存在も無視出来ない。
ロイヤルホテル<9713>が運営する「リーガロイヤルホテル(大阪)」。大阪のビジネス街である中之島に立地するこの名門ホテルは、「大阪の迎賓館」の異名があるように、関西財界の各セレモニーに利用されるほか、諸外国のVIP、また皇室ご一家が来阪した際のご宿泊に利用される超高級ホテルでもある。今回、同ホテルは真下に「京阪中之島線」を昨年10月開業させた京阪電気鉄道<9045>と手を組み、「大阪・京都二都物語」という京阪電車、京都市営地下鉄・バスの1日乗り放題切符をセットにした割引宿泊プランの提供を開始。大阪・京都双方の観光を楽しみ、しかも高級ホテルの非日常空間を味わいたいという宿泊旅行者の取り込みを図っている。さらに「定額給付金 宿泊プラン」も今年6月30日まで実施。特に今や大阪の代表的観光スポットとなったユー・エス・ジェイ<2142>が運営する「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」のスタジオパス1日券がセットになった、1泊1名朝食付き12,000円(所謂、定額給付金支給額と同額)プランなどは、同ホテルの水準を考えれば破格の特典サービスであり、ゴールデンウィークに向けての人気サービスとなることが見込まれる。
西日本旅客鉄道(JR西日本)<9021>のグループ会社が運営する「ホテルグランヴィア大阪」はJR大阪駅ビルに入居し、その抜群のアクセス環境を最大限に生かして、大阪は勿論のこと、関西一円を観光する宿泊客の取り込みに注力している。特に高級ホテルでありながら、日帰り(時間利用)プランを設けているのはまさに「地の利」を生かしたサービスと言え、実際利用頻度も高い。
阪急阪神ホールディングス<9042>のグループ会社が運営する「大阪新阪急ホテル」も京都・宝塚・神戸に路線が伸びる阪急梅田駅に直結している好立地を生かして、関西旅行を楽しむ宿泊客の取り込みを強化しており、特にグループが抱える大阪・関西の「集客装置」阪神タイガース、宝塚歌劇の観戦チケットをセットにしたプランなどは他社が真似の出来ないオリジナルサービスとして、同ホテルの強みとなっている。因みに同ホテルも定額給付金プランを今年5月11日から7月17日まで提供する。
勿論、大阪自体も「観光」出来るスポットを多く抱える。基本はビジネス都市であり、大阪府のGDPに占める割合も周辺府県に比べれば高くはないものの、周辺都市を観光する顧客の取り込み、今回の定額給付金・高速道路利用料金値下げといった追い風を生かさない手はない。
近畿日本鉄道<9041>、京阪電気鉄道<9045>は、各グループ会社が運営する「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」、「ホテル京阪ユニバーサル・シティ」、「ホテル京阪ユニバーサル・タワー」において、定額給付金、高速道路休日料金値下げを追い風に来園者の増加が見込まれる「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」の宿泊需要増加を好機と捉え、稼働率の向上を目指す。
また「道頓堀」、「吉本新喜劇」、「通天閣」など大阪最大の観光スポットが集積し、阪神なんば線の開通で近距離旅行者需要の増加も見込まれるミナミに立地する「スイスホテル南海大阪」は、南海難波駅真上にあり、駅リニューアルで相乗効果を狙える南海電気鉄道<9044>の協力を得て稼動率の向上を目指すほか、日本航空<9205>グループのJALホテルズが運営する「ホテル日航大阪」も、大阪を代表する繁華街・心斎橋に立地しショッピング・大阪市内観光に最適なアクセス条件を誇るうえ、ホテル内のレストラン・バーで利用出来る定額給付金割引クーポンを発行し、地元客の取り込みも図る。
<最後に>
日本は戦後「貿易立国」を掲げ、一貫して輸出に依存した経済成長を図ってきた。勿論、高度経済成長期には輸出の伸びに比例して所得向上に伴う内需の拡大も見られたが、少子高齢化社会に突入し、潜在的な内需縮小が懸念される現在、再び貿易収支への依存度を強めてきた。
しかし、今回の金融危機から派生した世界不況により、「貿易立国」だけで成長率を維持出来るのか、大いに疑問を突きつけられる事態に直面することとなった。そうした事態を受けて、今回の定額給付金、高速道路休日料金値下げによる内需掘り起こし策に繋がったのではないかと考えられる。勿論、こうした施策は迫り来る解散・衆議院選挙への与党の「小手先選挙対策」との評価もあり、事実上、国庫に手を付けたことで、後に必ずや「ツケ」が廻って来るとの懸念も強い。
また肝心要の内需に回っているかと言えば、そう単純な話でもないようである。例えば高速道路において、開始2週目に入った4月第一週には、花見シーズン到来時にも関わらず、利用者数が前年比1割程度しか伸びなかったとの結果が出ている。まさに所得減少・雇用不安の状況下で、単純に消費には回せない現実が浮き彫りになっている一つの証明であり、この高速道路料金値下げについては、ETC車に限ったこと、休日のみであること、普通車に限ったこと、さらに首都圏及び近畿圏内の都市高速道路に適用しなかったことから、同じ国民の間で不公平感が強まっている。人口の集中する首都圏と近畿圏の住民が身近に恩恵を感じ得ない点が、内需拡大に限界をもたらしている可能性も高い。
それでも「水飲み百姓」気質の日本において、内需拡大に向けた具体的な施策を実行したこと自体が、一つの前進であろう。むしろ最初から施策が予想通り展開すると考えること自体が間違いである。様々な試行錯誤を繰り返しながら、より効果の高い施策を考え、実行していけば良いのである。決して「浪費家」になるということではなく、効果的な内需拡大が進むことで、今回取り上げた観光産業、そうした産業装置が集積する関西などは特に「次世代型」経済発展システムに移行し、発展の持続に繋げられるほか、域内で活動する企業の将来性もまた、明るいものになっていくと考える次第である。