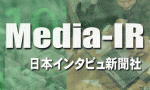���̔��㍂�P�A�O�O�O���~�˔j�A��s���ő�̂S�O�O�O�˔̔��̐��̊m����

�@
���{�����n�����W�W�V�W���i���P�j�̂O�W�N�R�������Z�i�A���j�́A�s���Y�̔����Ƃ��D���ɐ��ڂ������ƂŁA�o�험�v�͑O�X����T�O�D�R�����̂P�O�T���U�A�T�O�O���~�ƂȂ�A�P�O���A���ߋ��ō��v�X�V��B�������B������A��^�����𒆐S�Ƀ}���V�����̔������ː��̊g��ɉ����A���v���̌���𐄐i���Ă������ƂŁA�����v��ڎw���Ă����B
�@�O�W�N�R�����̔���グ�͑O�X����S�Q�D�P�����̂P�A�P�W�X���R�A�R�O�O���~�ƁA�n���ȗ����̂P�A�O�O�O���~��˔j�����B�o�험�v�P�O�T���U�A�T�O�O���~�i���T�O�D�R�����j�A�����v�S�U���S�A�U�O�O���~�i���Q�Q�D�U�����j�B�Ȃ��A�P������̗��v�͂P�R�T�~�T�U�K�i�O�X���͂P�Q�U�~�V�S�K�j���B
�@�P������̔N�Ԕz�����͂U�O�~�B�z�������S�V�D�R���i�O�X���͂S�S�D�R���j�A�����Y�z�����T�D�S���i���S�D�U���j�������B
�@�Z�O�����g�ʂŌ���ƁA�s���Y�̔����Ƃ̔��㍂�́A�O�X����S�X�D�R�����̂P�A�O�S�W���T�A�S�O�O���~�B�}���V��������ɂ����āA�}���V�������n�������O�X�N������U�P�D�U�����̂Q�A�S�W�V�˂ƍD���ɐ��ڂ������Ƃ������v���B
�@�s���Y���ݎ��Ƃ̔��㍂�R�P���Q�A�R�O�O���~�i���S�Q�D�T�����j�B�I�t�B�X�r���̎擾�ɉ����A�s���Y���ݎ��ƋƖ��̉�Ђ��R�ИA���Ώۂɉ��������ƂŁA���ݕ����ۗL�c�����O�X����Q�{�̂U�P�S���~�ɑ��������B
����s���ő�ƂȂ�N�ԂS�O�O�O�˂̃}���V���������̐��m����
�@���{�����n���́A�P�P�N�R�����܂łɁA��^�}���V�����̋������g�傷��ƂƂ��ɁA���v���̌�������߂Ă������ƂŁA�o�험�v�͉ߋ��ō��v�̂P�T�O���~�i�O�W�N���є�S�P�D�T�����j�������ށB�P�P�N�R�����̔��㍂�Q�A�O�R�O���~�i�O�W�N���є�V�O�D�V�����j�A�o�험�v�P�T�O���~�i���S�P�D�T�����j�A�����v�W�O���~�i���V�O�D�Q�����j��\������B
�@�����v�̎�v���́A�}���V���������̐��̊m�����B�O�W�N�R�����̎�s���ɂ�����}���V�������n���ː��ł͋ƊE�Q�ʂƂȂ���{�����n�������A��������N�ԂS�A�O�O�O�ˑ̐����m�����邱�ƂŁA�ƊE�g�b�v�ɗx��o�悤�Ƃ���B
�@���̂Ȃ��Œ��ڂ����̂��A��^�}���V���������̔̔����B�O�W�N�R�����ł݂�ƁA���ː��V�T�O�˂́u���C�f�B�A���g�V�e�B�����u�V���v�ȂǑ�K�͂R�����̔���グ�������ȏ���߂Ă���B��������Ђ͑��ː��R�S�U�˂́u���F���[�i�`�k�j���[�^�E���v�i�_�ސ쌧���l�s�j��A���ː��S�Q�R�˂́u���F���[�i�~�V���v�i�����s�~�s�j�ȂǁA���v���̍����Q�O�O�ˈȏ�̑�^�����̔̔��ɒ��͂��Ă������ƂŁA���v�g���}��B�u��^�����͎��v�����ǂ��A�Ɛтɂ������ɍv������v�Ɖ�Б��B
���������R����Ă���B��̃f�B�x���b�p�[
�@����ɁA���Е����}���V�����́A���p�I�Ńf�U�C�������L�x�ȓ������i��t�������Ă������ƂŁA���Ѓ}���V�����̕t�����l�̌����}���Ă����B�O�T�N�P�O���Ɏ��p�V�ēo�^�����u�I�[�v���G�A���r���O�o���R�j�[�v�́A���s���S���̃o���R�j�[���R���Z�v�g�Ƀ}���V�����̕t�����l������B�u�]���̉��s���Q���̃o���R�j�[�t�}���V�����ɔ�ׁA�I�[�v���G�A���r���O�o���R�j�[���R�O�O���~���l�i���グ�Ĕ̔����邪�A����s���͍D���v�Ɖ�Б��B
�@�I�[�v���G�A���r���O�o���R�j�[�̓��������O�W�N�R�������݂̂Q�O������A�O�X�N�R�����܂łɂU�P���ɂ܂Ŋg�債�Ă����B
�@�O�W�N�R���ɃT�b�V�S�̂ˏグ�邱�ƂŁA���g���̑S�J������������Ƃ����A�u���ˏグ�T�b�V�v�̓������擾�����B�܂����Ђ͉ԕ���Ƃ��Ă��L���Ƃ����u�G�A�V�����[�v�̓�����\�����B
�@��Б��ł́u�i���{�����n���́A�j�������R����Ă���B��̃f�B�x���b�p�[�v�Ƃ��邪�A�����̏��i���͓��Ѓ}���V�����̕t�����l����ɍv�����Ă����Ɗ��҂����B
�� �s������ǂ�����
�@���̂悤�ɏZ��s���Y�s��̊����A���ЂɂƂ��Ēǂ����ɂȂ��Ă���B���Ђ����͂����s���ł́A�l�������⎩�R���ȂǂŁA��s���̐l���͔N�ԂQ�R���l������������B����ɔ�����s���ł́A�N�ԂV���ˈȏ�̏Z����v���������Ă���Ƃ����B
�@�Ƃ��낪�����̒����̃f�B�x���b�p�[�́A�O�V�N�ĂɎ{�s���ꂽ���z��@�̉����ɔ����A�}���V�����̋�����������Ă���̂����B�������ɔ����A��s���ɂ�����}���V�������v���g�債�Ă���B���̒��ŁA���{�����n���͔N�ԂS�A�O�O�O�˂̃}���V���������̐����m�����Ă������ƂŁA�g�傷���s���}���V�����s��ɍU���������Ă����B
�@�����}���V�������Ƃɂ����ẮA�p�n�̎擾���A����̗��v�����E����傫�Ȍ����͂ɂȂ�B���{�����n���́A�O�W�N�R�����܂łɂR�A�P�V�S���~�̗p�n�̎擾�����������B���Ђ́A�����o�c�v��̍ŏI�N�x�ɂ�����P�P�N�R�����܂ł̃}���V�������㍂�̍��v�R�A�X�R�O���~��\�肵�Ă���A�v��̂W�P���̗p�n���擾���Ă���B���Ђ̃}���V���������̐��͐����Ă���B
�@���̂悤�ɓ��{�����n���́A�����Ȏs�����w�i�ɁA��^�����̒�A�}���V�����t�����l�̌����}�邱�ƂŁA�P�P�N�R�����̕s���Y�̔����Ƃ̔��㍂�P�A�W�T�O���~�i�O�W�N�R�������є�V�U�D�T�����j��ڎw���Ă����B
�@��Б��́u�i�O�U�N�R��������O�W�N�R�����Ɏ��{���ꂽ�j�O�����o�c�v��̌��ʁA�R���N�̌o�험�v�͂Q�S�S���~�Ɠ����v��̂Q�P�S���~���������B�V�����o�c�v��ɂ�����R���N�̌o�험�v�́A�O�����o�c�v�������R�Q�O���~��ڕW�Ƃ���B�O�����o�c�v����啝�ȃA�b�v��ژ_�ށv�Ƃ��A�v��B���Ɍ������M��[�߂�B
�� ���{�C���^�r���V�� Media-IR 2008.06 |
���W