| 資源株相場の背景 |
①東西冷戦終結と平和の配当
世界は長い間、アメリカと旧ソ連の東西対立が続いた。世界大戦による国民生活の疲弊と核の脅威により平和を求める空気が強まった。1989年11月9日にベルリンの壁が崩壊し冷戦の終結が誰の目にもはっきりと焼きついた。以来、世界は競って「平和の配当」を求めて経済発展に走った。当然、資源の消費量拡大につながった。
②新興国の躍進
旧東側諸国は安くて豊富な労働力を武器に西側から資金、技術を導入しモノ作りに乗り出した。BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)の躍進が目立った。特に、人口13億人を擁する中国は「眠れる獅子」から醒め、2008年8月にはオリンピックを開催できるまでとなった。豊かになれば当然、食糧等も含め資源消費は増大する。
③「2から4へ」の法則
動物は進化すれば4本足から2本足となる。進化した人間は逆に多くを求めるようになる。その代表が自転車、オートバイの2輪車から4輪車の自動車の普及。当然、ガソリンの消費は2倍にとどまらず、数倍に増加する。原油価格押し上げの最大の背景となる。
| 短期的な展望 |
①オリンピック終了
大きなイベント(お祭り)は、需要の「山」を作る。中国はオリンピック開催のために、社会資本の整備を進めた。日本の公園から、スベリ台が消えてしまうほどの異常な鉄鋼需要となった。その需要はピークを過ぎた。国民の家計においてもテレビ購入などの消費も一巡した。お祭り需要の反動がどのあたりで落ち着くか、当面の最大の見所。
②アメリカのスタグフレーション
資源高によるインフレはアメリカだけの問題ではないはず。むしろ、アメリカは原油、鉱物資源の高騰に対しては、武器のひとつである穀物価格の上昇でカバーできたはず。しかし、アメリカには、サブプライム問題による深刻な景気後退がある。8月の失業率は6.1%に悪化した。2003年9月以来の悪いデータ。物価高と景気後退が同時に進むスタグフレーションは経済運営には容易でない。アメリカは原油高を望んでいない可能性がある。
③オペックの減産
オペックは原油高騰が続いていた最中でも増産をしなかった。しかし、原油先物相場が100ドル近くまで下げてきたら、日量約50万バレルの減産を40日以内に実施することを決めた。このことは、原油相場が高値から3割下げの100ドル台をひとつのフシとみていると判断できる。
| 中長期的な展望 |
①豊かさを知った新興国
振興国のキーマンはやはり中国。オリンピックを終えた中国は、オリンピック後に不況を迎えた日本や韓国と違って、国土は広いし人口も多い。オリンピック反動はそれほどの時間をかけず盛り返してくる可能性は十分ある。社会資本が整備され、国民の生活が衣・食・住のすべてにわって豊かさをしった国民は簡単には後戻りはできない。中国にかぎらず、インド、ブラジル、ベトナムなどの経済発展第2ラウンドはこれからである。
②埋蔵量の減少
振興国の経済発展が進み、原油などの資源消費が進めば、今まで言われていたより早いペースで埋蔵量を食いつぶす。世界の埋蔵量は1900億キロリットルといわれる。内、55%程度が中東地区となっている。未確認埋蔵地帯もあるだろうが、開発されるのは原油相場がもっと高くなってからだろう。ところで、1バレル=107ドル、為替を1ドル=107円で計算すると1リットル当りの原油は約72円。天然水よりも若干安く、原油価格の割安感はある。
③国際緊張
原油価格高騰に連れて天然ガスも上昇。産出国ロシアの懐を大きく潤わせている。サブプライム問題でアメリカの金融界は、がたがた。ロシアの資金にまでは救済を仰いではいないが、経済力をつけたロシアは国際軍需バランス上、目が離せない。既に、ロシアは「新冷戦」も辞さず、と強い態度に出ている。底流には資源争奪をめぐっての対立が激しくなる可能性は強い。
変動こそ儲けのチャンス! 初秋に贈る「特別講演会」を開催
『資源&商品』の右肩上がり相場は不変!? 新興国の発展はこれからが本番
自民党の総裁選を控え、政治ジャーナリストの岩見隆夫氏が『風雲急』の政局を占う
原油価格と国際商品相場に第二ラウンドはあるか!? 年後半の商品市況はいかに・・
9月20日(土) 東京証券会館8Fホール 14:00~ 入場無料先着順(320名)
>>詳細はこちら
提供 日本インタビュ新聞 Media-IR 2008.09 |特集

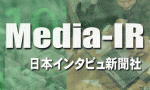

 ■10年前に比べ原油相場は15倍、この間の日経平均は66%の下落
■10年前に比べ原油相場は15倍、この間の日経平均は66%の下落