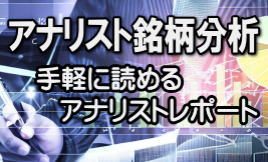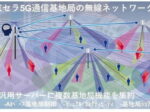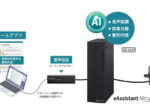- Home
- 小倉正男の経済コラム
- 【小倉正男の経済コラム】1ドル150~160円超 令和の「経済敗戦」
【小倉正男の経済コラム】1ドル150~160円超 令和の「経済敗戦」
- 2024/5/6 08:23
- 小倉正男の経済コラム

■4月雇用は予想を下回り、長期金利低下しNY株価は上昇
米国労働省が発表した4月雇用統計だが、景気の現状を反映するといわれる非農業部門雇用者数は17万5000人増加となり、予想雇用者数24万人を大きく下回る結果となった。前月は30万3000人増(改定値31万5000人増)の雇用者数だった。さすがに雇用者増はやや鈍化となった格好である。
失業率は3・9%(予想3・8%)と前月の3・8%から悪化している。平均時給は0・2%(予想0・3%)で前月の0・3%を下回った。労働需給の過熱感はやや低下の兆しがみえる。ただし、4月単月ベースの推移であり、今後のトレンドを指し示すかどうかは何ともいえない。
「9月には利下げが行われる」(市場筋)といった金利低下期待がにわかにぶり返したが、この傾向が5月、6月と継続しなければ利下げのスケジュールは見込めない。現状では利下げ期待は掛け声というか、少し気が早いということになる。
だが、久々の“景気鈍化”を示す指数に市場は反応している。米国国債10年物利回りは4・50%に大幅低下している。円は一時1ドル160円台に突入したが、巨額の為替介入で1ドル153円台となっていた。4月雇用統計発表で一時151円台になり、その後も152円台と円高に転じている。前週末のNY株式市場は450ドル高、ナスダックは315ドル高と大幅上昇している。
■原油高は高止まり、インフレの火種が残る
米国経済、あるいは景気の底堅さは少し後退しているとしてもインフレが簡単に収束に向かうとはいえない。地政学的リスクが残っている。地政学リスク、端的にいえば戦争だが、これがもたらしているのが原油高である。
ロシアのプーチン大統領によるウクライナ侵攻は長期化が避けられない。4月には米国バイデン大統領が610億ドル(9兆4000億円)のウクライナへの武器・装備品の支援予算を成立させた。米国はG7にも呼び掛けて最大500億ドル規模のウクライナ軍事支援を実現する提案を推し進めている。原資はウクライナ侵攻制裁で凍結したロシア資産から得られる利益を充当するというプランである。
さらに中東では「ガザ戦争」(イスラエルハマス戦争)が地獄の様相となっている。終わりはなかなかみえない。イスラエルのパレスチナ人への過剰なほどの攻撃は世界的に顰蹙をかっている。休戦交渉が行われているが、おそらく長期化が避けられない。
原油価格は、「イスラエルイラン戦争」で1バレル80ドル台後半まで上昇している。もし戦争が深刻な局面に突入すれば、1バレル90ドル台~100ドル台が懸念された。その後、原油高は小康を得て、現状は1バレル70ドル台後半まで低下しているが、高止まり感は拭えない。原油が高騰するような局面になれば、インフレ懸念再燃で米国の利下げ機運は後退することになりかねない。
■企業・産業の保護優遇でサバイバル力は衰弱
いまの1ドル150円台~160円超という円安ドル高は、企業・産業の盛衰が反映されているようにみえる。端的に比較すると、日本には米国の「GAFAM」のような世界的な現代テクノロジー企業がひとつもない。国力ということになるのかもしれないが、個々の企業・産業の競争力衰退が否めない。
経済記事に感情は無用だが、厳しくいえば令和の「経済敗戦」と受け止める必要があるかもしれない。昭和には1ドル2円の戦前から、戦後は1ドル360円になった。その令和版が1ドル160円超ということになる。
為替は円安、金融はマイナス~ゼロ金利、労働は非正規社員の増加、それに雇用調整助成金など各種補助金など――。ここまで企業を優遇するのかと保護政策を採ってきている。そうした保護優遇政策は、雇用の安定を生んだが企業がサバイバルを図ろうとする本能を衰弱させた面がある。マイナス~ゼロ金利でしか生存できない「ゾンビ企業」を生んできたのも事実である。
そのうえ日米の金利差、日本の政策金利0・10%に対して、米国の政策金利5・50%。これだけ金利差があれば円安も致し方ない。結局、円の価値を決めるのは米国の金利動向である。地政学リスクが残りインフレ懸念のくすぶりを払拭できない。そうした様相が続いており、円は最も脆弱な通貨という位置にとどまるしかない。(経済ジャーナリスト)
(小倉正男=「M&A資本主義」「トヨタとイトーヨーカ堂」(東洋経済新報社刊)、「日本の時短革命」「倒れない経営~クライシスマネジメントとは何か」(PHP研究所刊)など著書多数。東洋経済新報社で企業情報部長、金融証券部長、名古屋支社長などを経て経済ジャーナリスト。2012年から当「経済コラム」を担当)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)