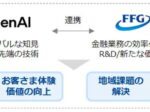【どう見るこの相場】「トランプ・リスク」再燃!兜町に暗雲、自己株式取得銘柄に光明か?
- 2025/2/25 08:26
- どう見るこの相場

■植田日銀総裁vsトランプ大統領、市場は「トランプ・リスク」に戦々恐々
「金曜日の引けピン」というには、迫力不足であった。兜町には、週末の金曜日の後場に株価が高くなり、とくに高値引けすると、翌週も強気相場が継続するとするアノマリーがある。3連休前の21日の日経平均株価は、3日ぶりに反発し取引時間中に売られた221円安から持ち直して98.90円高で引けたが、前場につけたこの日の高値には2には未達となった。案の定、続いて開いた米国市場では、ダウ工業株30種平均(NYダウ)が、748ドル63セント安と大幅続落し、1カ月ぶりの安値に落ち込み、為替も一時、1ドル=148円台と円高ドル安となって、きょう連休明け25日の東京市場は、強気相場どころか暗雲モクモクである。
21日の日経平均株価の後場高は、日本銀行の植田和男総裁が国会で、長期金利が急上昇するなら機動的に国債買入増額を実施し歯止めを掛けると発言したことが引き金となったが、続く米国市場では、これを上回るネガティブ・サプライズが待ち構えていた。週末に相次いで発表された経済指標が、いずれも下落して市場予想を下回り、2023年秋以来の低水準になったことが重荷になったが、その背景にあったのがトランプ関税の先行き不透明感である。
■兜町に吹き荒れる「トランプ・リスク」—投資家の選択肢は?
この日米両市場の好悪材料の先行きは、植田日銀総裁とトランプ米大統領の胸の内次第ということになるが、兎に角相手は、自らをナポレオンになぞらえ「トランプ・リスク」を拡大再生産中のトランプ大統領ある。仮に植田日銀総裁が、「トランプ・リスク」へ挑んだとしても火消しが可能かは不透明である。兜町の連休中の24日にオープンした米国市場では、NYダウは3営業日ぶりに反発したが、33ドル19セント高と自律反発程度にとどまった。トランプ大統領が、延期していたカナダ、メキシコへの追加関税を来月実施すると伝わったことが足を引っ張ったようだ。
「トランプ・リスク」が吹き荒れるマーケット環境下では、「売り、買い、休む」の投資スタンス、銘柄選択も悩ましいことこの上ない。こうなると頼りになるのは、英国流の諺の「天は自ら助くる者を助く」を実践する銘柄選択しかない。総論売り、各論買いの個別銘柄物色で、自ら株高努力を続ける健気な銘柄には「相場の神様」も微笑んでくれるということである。折柄、3月期決算会社の第3四半期(2024年9月~12月期、3Q)業績の発表も2月14日にピークを通過して1週間が経過した。
■自己株式取得が救世主?「相場の神様」が微笑む銘柄を探せ
3Q純利益は、日本経済新聞の集計では前年同期比15%増と2年連続で過去最高を更新しており、3月期通期業績を下方修正する銘柄より上方修正する銘柄のウエートも高かった。とういことは「自ら助くる」銘柄は、好業績銘柄というだけでは当たり前すぎて十分ではない。「天が助くる」資格条件を充足できる銘柄といえば、まず自己株式取得銘柄となるはずである。「相場の神様」が微笑んでくれるのを期待するということである。
自己株式取得は、株主への利益還元策の一翼を担うが、このほか政策保有株売却の受け皿、自社株価の割安放置へのアピール、業績下方修正の際の株価下落を押しとどめる株価防衛策などさまざまな発動要因がある。昨年2024年も、前々年7割増の約17兆円と3年連続で過去最高を更新したと集計されているが、今年2025年も、1月年初から3連休前の21日までで255銘柄が、自己株式取得枠の設定を発表している。所属業種も所属市場もさまざまで、取得株式総数も発行済み株式数に占める比率も取得総額も千差万別となっている。ただ、自らの株価を割安と内外に告知するアナウンス効果では共通しており、逆風が吹く相場環境下でもそれなりの健闘をしている。
■自己株取得で株価下支えする企業に注目
なかでも自己株式取得と増配、優待制度などのダブルセット、トリプルセット、フルセットなどの好材料を上乗せ発表した銘柄にはストップ高や昨年来高値にまで買い進まれた銘柄も出ている。そこで今週の当コラムでは今年1月以降に自己株式取得を発表した銘柄のうち、業績を上方修正しなお割安水準にある銘柄をスクリーニングした。18銘柄が浮上しており、「自ら助くる」銘柄を「天が助く」銘柄として注目することにした。強敵の「トランプ・リスク」を前に徹底抗戦を期待してスタンバイしたい。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)