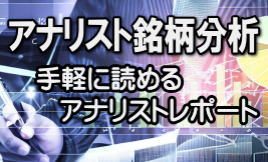【作家・吉田龍司の歴史に学ぶビジネス術】中小零細企業は「海賊」ビジネスで生き残りを図れ
- 2016/9/26 13:04
- 株式投資News

■業績好調は見かけ倒し?
中小企業の業績が好調のようだ。経産省の中小企業白書(2016)を見ても、経常利益は5.2兆円(大企業9.9兆円)と過去最高水準にある。
半面、気がかりなのが2011年以降、一貫して伸び悩む売上高だ。利益好調といっても内実は原材料費など変動費の減少、従業員など人件費の減少によるものであり、手放しで「いい」といえる状況ではない。こうした要因は無論この先どうなるかわからない。従業員の減少から人手不足が深刻化している業界もある。
財務面で余裕があるとするならば、経営者は目先のことも重要なのだが、今のうちに5年後、10年後の売上をいかに伸ばすかを考えるべきだろう。答えの一つは「技術の深掘り」である。他社に真似のできない専門性を持ち、「○○を頼むならあそこ」という強みを持たなければ、生き残りはますます難しくなることだろう。
■村上水軍は「海」に特化した技能集団
「戦国時代の中小企業」というべき存在は瀬戸内を席巻していた村上水軍だ。
村上水軍は海賊である。ここで誤解のないようにいっておきたいのだが、日本の中世の海賊とは、いわゆる「賊」を指すものではない。非常に業態の広いビジネスを営む、「海の総合サービス会社」といえるものである。
当時の瀬戸内には海で生計を立てている海賊、海辺の領主がたくさんあり、まるで大田区蒲田を彷彿とさせるような状況だったが、村上水軍はその代表格であった。
村上水軍は芸予諸島をホームグラウンドとしており、能島(愛媛県今治市)、来島(同)、因島(広島県尾道市)の三つの家があり、三島村上氏とも呼ばれる。来島、因島は地勢的に陸上の大名、つまり愛媛や広島の大企業との関係性が深いが、能島村上氏は非常に独立性の強い勢力だった。
瀬戸内海は古くから西国と畿内を結ぶ物流の大動脈であり、中世は多数の積荷を載せた商船が行き交っていた。一方、芸予諸島周辺は狭い水路、渦潮が逆巻く難所が多く、現代でも遭難事故が起きるほどのデンジャーゾーンである。航海技術に卓越し、海洋の地理に精通した専門集団へのニーズは大きかった。また、山陽側にも四国側にもずば抜けた陸上勢力が秀吉の登場まではいなかったので、瀬戸内は陸上勢力の緩衝地帯でもあった。ゆえに村上水軍のような海上勢力が伸びる土壌があったのである。
■技術を深掘れば新たなビジネスチャンスが見つかる
戦国時代の能島氏の当主であり頭領であり社長さんだったのが村上武吉である。
当時瀬戸内海を旅し、武吉が本拠とする能島城周辺を航海した宣教師のルイス・フロイスは能島氏の威勢に驚き、イエズス会の報告書で武吉を「日本最大の海賊」と記している。
能島氏の業態は以下のようなものだ。まず水先案内。これは現代の旅行業者のようなものである。次に海上警固。幕府や周辺の諸大名、商人たちの船の護衛である。そして通行料収入。能島氏らは各所に「海の関所」を設け、航行する船から通行料や荷物に応じた税金を徴収する権利を有していた。
傭兵業務もある。毛利氏や大内氏、織田氏らは海戦を得意とする能島氏を味方に付けることを勝敗に直結する問題と考え、さまざまな手で勧誘を行っている。
他に密貿易、漁労もやっていたほか、どうやら造船もやっていた可能性もある。確たる史料はなく、伝承しかないのだが、瀬戸内は近世から現代に至る造船のメッカでもあり、その発祥が村上水軍と無縁だとはとても思えない。
さらに廻船業務を行っていたと考えられることから、金融、つまり決済業務的なこともやっていたように思える。瀬戸内海には村上水軍と通じた勢力があり、武吉は津々浦々にネットワークを持っていた。もちろん村上氏は三島の間でも連携は緊密だった。津々浦々での取引の円滑化は当然できたはずである。
こうして見ると、当初水先案内や警固業務から始まった村上水軍は、海洋に関する技術の深掘りを進めることで「海に関することすべて」に携わっていた公算が大きい。ゆえに陸上勢力は彼らを頼りとし、「海のことなら村上水軍に頼もう」となったわけである。
技術の一点特化もいいのだが、深掘りをしていくとそれに付随して色々なビジネスチャンスが必ず見えてくる。大切なのは村上水軍の「海」のような中心テーマを持ち、その中心テーマにこだわり続けることであろう。テーマに関連して儲かりそうであれば、それは生かしたほうがいい。ただし、下手にテーマから外れると「陸に上がった河童」になってしまう。武吉はその点をよく心得ていたマネジャーだったのである。
(作家=吉田龍司 『毛利元就』、『戦国城事典』(新紀元社)、『信長のM&A、黒田官兵衛のビッグデータ』(宝島社)、「今日からいっぱし!経済通」(日本経営協会総合研究所)、「儲かる株を自分で探せる本」(講談社)など著書多数)