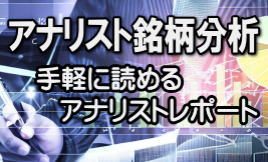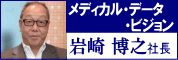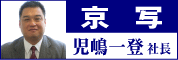【作家・吉田龍司の歴史に学ぶビジネス術】徳川家康の三現主義
- 2015/7/24 12:10
- 株式投資News
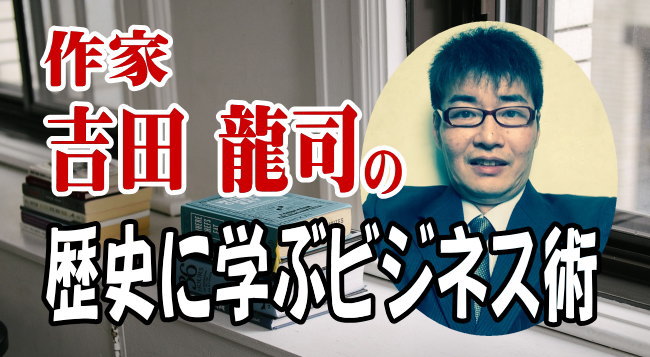
■現在にも通じる経営の基本
今年は徳川家康の没後400年。岡崎、浜松、日光といったゆかりの地では記念イベントが盛んだ。さて家康といえば連想されるイメージは、「忍従の人」である。人質生活を耐え、涙を呑んで妻子を殺し、そして59歳で満を持して天下取りに臨んだ75年の生涯。有名な『人の一生は重き荷を負うて~』の格言や、山岡荘八の同名小説の印象も強いのだろう、多くの戦後の経営者は、「耐え忍ぶ”家康を手本とした。
ただし、もう一点、経営者・家康には見逃せない美徳がある。それが『三現主義』と呼ばれるものだ。
三現主義とは、現場・現物・現実の三つの「現」を重視する考え方だ。何か経営上の問題が発生したとき、「現場に直接行く」、「現物(現状)に直接触れる」、そして「現実を把握する」べき、というものである。
■アナリスト的存在の「如水」は敗れた毛利輝元の三現不足を指摘
ある地区での売上が伸び悩んだ、工場ラインに問題がおこった、顧客からクレームがきた。こうしたとき自らの五感で3つの「現」を捉えれば、必ず解決のヒントは見つかる。近年は「三現」に原理・原則の「二原」を加えた「五ゲン主義」という言葉も生まれている。要は、パソコンの前に座っているだけのマネジャーが一番ダメなのである。もちろん机の前でやることはあるにせよ、机上の空論はしょせん空論に過ぎないのだ。
天下取りの大一番・関ヶ原の戦い(1600)で家康は東軍の総大将となり、江戸城で周到な準備(多数派工作)を重ねた上で関ヶ原へ駒を進めた。
家康は「戦う前に勝つ人」とも言われるが、正しくは「戦う前に勝つ準備をした人」である。戦場では何が起るかわからないし、実際関ヶ原は予期せぬハプニングの連続となった。机上の計算だけではあてにならないからこそ、家康は最前線の現場へと赴いたわけである。
一方、西軍の事実上のリーダーは石田三成だったが、総大将は毛利輝元(元就の孫)だった。輝元は従来”お飾りの大将”といわれてきた。しかし近年の研究で、彼が積極的に戦いに関与し、四国、九州へ大兵を送っていた事実がわかってきた。この大政変を機に、輝元は西国に毛利の一大帝国を築こうとしていたのである。
輝元も家康同様、領国の広島から大坂城に入った。しかしそこから一歩も動かず、すべての命令は大坂城から出した。そしてその姿勢は関ヶ原本戦という大一番を前にしても変わらなかった。甘いとしか言いようがない。
関ヶ原は三現主義の家康の勝利に終わり、輝元は領土拡張どころか、112万石→37万石に大減封され、萩の地へ追いやられてしまった。
実はこうしたトップとしての輝元の弱点を早くから指摘していたのが黒田如水(官兵衛)である。関ヶ原25年前の天正3年(1575)、如水は「輝元には大将の器量がない。その理由は戦いに臨み、自身の出馬があまりないことだ」(『黒田家譜』)という人物評を残している。希代のアナリスト・如水は輝元の三現主義不在をはっきり見抜いていたのである。
続く大坂の陣(1614~15)でも家康は後方に陣することをよしとせず、高齢を押して戦場の最前線へ向かった。あわや真田信繁(幸村)に討たれかけるというリスクを犯したのだが、それでも「三現」にこだわったのである。一方、敵方大将の豊臣秀頼は大坂城から一歩も出ないまま、あえない最期を遂げた。
たとえば家康がのんきに駿府城(当時の在城)を動かず、大坂城攻めを秀忠に任せたとしよう。また秀頼があの千成瓢箪の旗印を掲げて出陣していたとしよう――ならば歴史は変わったのかもしれないのである。徳川方にあった豊臣恩顧の大名に動揺が走らなかったとはとても思えないし、城方に寝返る者が続出する可能性もあったのではないか。結局、現場では何が起るかわからないのである。だからこそ家康は最後の最後まで、三現主義を貫いたといえるのだ(作家・吉田龍司=都留文科大学英文科卒業、歴史と経済分野を得意とする)